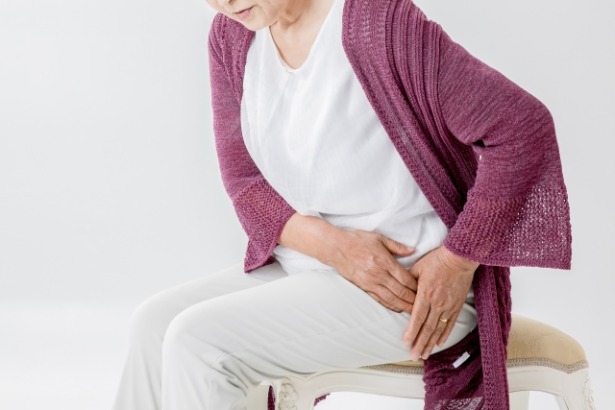 大阪市東住吉区にある医療法人金子外科では、地域の皆様のホームドクターとして、患者様お一人ひとりに丁寧で継続的なサポートをご提供しております。このブログでは、患者様の健康維持に役立つ情報をお届けしてまいりします。骨粗しょう症は、特に閉経後の女性に多く見られる病気です。骨粗しょう症の治療の基本は「運動」「食事の改善」「薬物療法」の組み合わせです。特に運動は骨密度の向上と転倒予防に大きな効果があります。この記事では家庭でも安全に実践できる骨粗しょう症対策の運動についてくわしくご紹介します。
大阪市東住吉区にある医療法人金子外科では、地域の皆様のホームドクターとして、患者様お一人ひとりに丁寧で継続的なサポートをご提供しております。このブログでは、患者様の健康維持に役立つ情報をお届けしてまいりします。骨粗しょう症は、特に閉経後の女性に多く見られる病気です。骨粗しょう症の治療の基本は「運動」「食事の改善」「薬物療法」の組み合わせです。特に運動は骨密度の向上と転倒予防に大きな効果があります。この記事では家庭でも安全に実践できる骨粗しょう症対策の運動についてくわしくご紹介します。
骨の健康を維持するための基本知識
骨粗しょう症の主な原因は加齢、女性の場合は閉経によるエストロゲンの減少、そして生活習慣にあります。骨密度は20歳頃にピークを迎え、40歳代までは維持されますが、その後徐々に低下していきます。
特に女性は閉経後、骨密度を維持する働きのあるエストロゲンの分泌が減少するため、骨密度が急激に低下します。また、喫煙、多量の飲酒、過度なダイエットも骨の健康に悪影響を及ぼします。
一度低下した骨密度を大幅に回復させるのは難しいため、若いうちからの「骨の貯金」が重要です。しかし、中年期以降でも生活習慣の改善により、骨密度低下のスピードを緩やかにして骨粗しょう症のリスクを減らすことができます。諦めずに取り組みましょう。
骨粗しょう症の治療目的と方法
骨粗しょう症治療の最大の目的は骨折を防ぐことです。そのためには、骨密度を増やして骨を丈夫にすることと、骨折の原因となる転倒を防ぐ体づくりが重要となります。
治療の基本は「運動」と「食事の改善」であり、必要に応じて「薬物療法」を併用します。今回は特に「運動」に焦点を当ててご説明します。
運動が骨に与える効果
骨には、負荷をかけると強くなり、負荷をかけないと弱くなるという特性があります。適切な運動は骨密度を増加させる効果があることが科学的に証明されています。逆に、長期間寝たきりの状態や宇宙飛行士のように無重力環境で過ごすと、骨密度は急激に減少します。骨を強くするには「衝撃」が効果的です。特に閉経前の女性では、1日50回のジャンプで骨密度の上昇が報告されています。バレーボールやバスケットボール、縄跳び、ジョギングなども効果的です。
しかし、高齢者の場合は腰や膝を痛める可能性があるため、強い衝撃が加わる激しい運動は避け、まずは安全な運動で足腰を鍛えることが大切です。筋肉がついてきたら、少しずつ他の運動にも挑戦してみましょう。
自宅でできる骨粗しょう症対策の運動
ご紹介する運動は、安全かつ効果的に骨と筋肉を鍛えることができます。いすや机は安定したものを使用し、平らで滑らない場所で行いましょう。無理のない範囲で実践してください。
片脚立ち
転倒予防に効果的
脚の付け根の筋肉を鍛え、バランス力を高める運動です。
- 背筋を伸ばして立ち、片脚を床につかない程度に上げて1分間保ちます。
- 左右の脚でおこない、1日3回程度を目安にしましょう。
しこ踏み
横方向のバランス力や脚の筋肉を鍛える運動です。
- 足を肩幅に開き、腰を落とします。
- 片脚をバランスが保てる高さまで上げ、地面をたたくように落とします。
- 左右10回ずつ、1日3セットを目安におこないましょう。
かかと落とし
つま先立ちから勢いよくかかとを落とすシンプルな運動ですが、効果的に骨に衝撃を与えます。
- 足を肩幅に開き、背筋を伸ばして立ちます。
- つま先立ちをした後、かかとを勢いよく下ろします。
- 膝や股関節に痛みがある場合は、勢いを弱めるか膝を少し曲げてください。
- 10回を1セットとし、1日3セットおこないましょう。
壁押し&かかと落とし
手首、肩、太もも付け根、腰を鍛える総合的な運動です。
- 足を肩幅に開き、背筋を伸ばして立ちます。
- かかとを上げながら、手のひらで壁を勢いよく押します。
- 手首、肘、肩に痛みがある場合は、壁を押す力を軽減してください。
- 10回を1セットとし、1日3セットおこないましょう。
骨粗しょう症対策の運動は、継続が成功のカギ
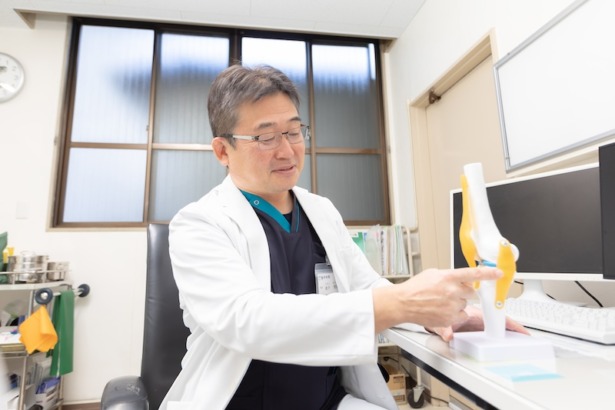 骨粗しょう症は自覚症状がないまま進行することが多い病気です。骨粗しょう症対策の運動は、無理なく継続できることが最も重要です。今回ご紹介した運動は、自宅で手軽におこなえるものばかりです。毎日の生活の中に取り入れて、骨と筋肉を効果的に鍛えていきましょう。また、運動だけでなく、カルシウムやビタミンDを多く含む食品を積極的に摂ることも骨の健康には欠かせません。骨粗しょう症の治療は、運動と食事の改善が基本です。大阪市東住吉区にある医療法人金子外科では骨密度検査を実施しており、最新の検査機器を用いた骨粗しょう症の診断・治療はもちろん、個々の患者様に合わせた運動指導もおこなっています。ご不安や疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
骨粗しょう症は自覚症状がないまま進行することが多い病気です。骨粗しょう症対策の運動は、無理なく継続できることが最も重要です。今回ご紹介した運動は、自宅で手軽におこなえるものばかりです。毎日の生活の中に取り入れて、骨と筋肉を効果的に鍛えていきましょう。また、運動だけでなく、カルシウムやビタミンDを多く含む食品を積極的に摂ることも骨の健康には欠かせません。骨粗しょう症の治療は、運動と食事の改善が基本です。大阪市東住吉区にある医療法人金子外科では骨密度検査を実施しており、最新の検査機器を用いた骨粗しょう症の診断・治療はもちろん、個々の患者様に合わせた運動指導もおこなっています。ご不安や疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。